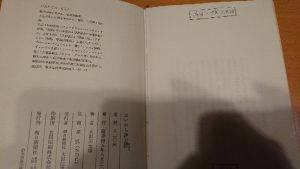NHKテキストを読書にカウントするというのもどうかと思うのだけど、好評のようなので読んでみた。『はじめての沖縄』(恐らく名著と称してもいい)の著者が講師であるというのものも、気になったポイントの一つ。
ブルデューは共著『遺産相続者たち』をだいぶ前に買って積ん読しているだけ。
序盤の肝と言うべき、「私たちの日常的な文化的行為、すなわち趣味は、学歴と出身階層によって規定されている」(本テキストp21)という点に関しては、人によっては衝撃的なのかもしれないけど、まぁそうだろうな、と特に新鮮味なく受け止めてしまうのだが、そもそもそういう受け止め方をできるということ自体、私の思考が「そういう」履歴を重ねてきたから、ということである。
で、このあたりについては、さらりと読み進めてしまえるので、むしろ面白いというか自省を迫られるのは、終盤の「あらゆる行為者は合理的である」「他者の合理性」の部分。このへんを読むと、たとえば、社会学者ではないがジャーナリストとしてトランプ支持者の考え方や生活を追っている金成隆一の『トランプ王国』『トランプ王国2』あたりを読み直したくなる。
しかし、そうやって「他者の合理性」に耳を傾けられるかどうかというのも、かなりの確率で非対称な関係になりそうだよなぁ…。
番組の方を観る予定はないけど、テキストだけでも非常に分かりやすく読みやすいので、これはオススメです。