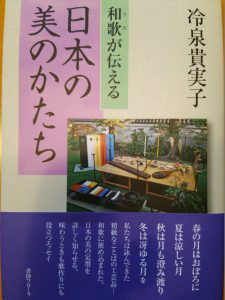この1年、いま住んでいるマンションの管理組合の理事をやっているのだけど、理事長から「面白かったよ」と貸してもらった本。
後半の章で紹介される、いわばベストプラクティスは、「こんなのウチのマンションじゃ無理だよな~」とも思うし、そういうマンションに住みたいかと言われると、決してそうは言い切れないような例も出てくる。が、まぁ個別具体的な状況が違うだけで、基本は共通するのかな……。その意味で勉強にはなりました。
ところで、これは編集者レベルの問題だと思うし、この本に限ったことではないのだけど、本文中では西暦で書かれているのに、グラフの時間軸は元号表記になっているとか、本文中で「いまからxx年前」と書かれているとか(「いま」が何年なのか奥付を確認する必要がある)、そういうのは何とかしてほしい……。